
環境活動で「食のマーケティングカンパニー」はさらに進化する
国分グループ本社株式会社
執行役員 経営企画部長 兼 サステナビリティ推進部長 青山知夫さん
国分グループ本社株式会社
1712年醤油醸造業として創業。明治期に醤油醸造業を廃止し、広く食品を取り扱う卸売業となり、現在に至る。国内外約1万社のメーカーから約60万アイテムの商品を仕入れ、スーパー、コンビニエンスストアなどの小売店や外食産業約3万5000軒に販売。また、世界各国へ日本食を輸出する貿易事業、中国・ASEANエリアでの卸・物流事業で、海外における食の流通の最適化にも取り組む。
「食のマーケティングカンパニー」として進化を続けるために、流通業界全体を見据えて環境配慮の取り組みを図る国分グループ。そのために欠かせない、従業員一人一人の環境全般の知識習得に向けて、eco検定の受験を全従業員に推奨している。現在、全従業員の約3割がエコピープル(=eco検定合格者)となっており、受験者への充実したフォロー体制や、今後の展望を伺った。
 流通業界として環境問題は身近なもの
流通業界として環境問題は身近なもの
―いま流通業界では、どのような面で環境への配慮が課題になっているのでしょうか
当社は酒類の取り扱いも多いのですが、たとえばワインで使うぶどうの生産地が変わってきていることは、よく耳にします。地球環境の変化、特に各地の平均気温の上昇を感じる現象のひとつです。食品を取り扱う私たちの業界は、生鮮にしても加工品にしても、その原料となる農水産物に直接影響を与える環境問題は、とても身近な社会課題のひとつです。
当社は食品の総合卸売業ですから、相当量の物流を扱っています。常温・冷蔵・冷凍など、各温度帯の食品を厳格に管理することも求められますので、環境への負荷は大きくなってしまう。社会に対してその責任を果たす意味でも、率先して環境問題に対して働きかけていく必要性を感じておりました。
―創業290年の節目(2002年)に、国分グループ本社の行動憲章・行動規範「平成の帳目」を策定され、その中で環境活動に積極的に取り組むことを掲げられました。eco検定の推進もその一環でしょうか。
はい。従業員が環境問題に携わる入口として、eco検定が非常に良いきっかけになると考え、当社では全従業員に対してeco検定の受験を推奨しています。環境全般の知識習得や、従業員の環境マインド「Eco-ゴコロ」の醸成を図る取り組みの一環です。
現在、国分グループは「地域密着 全国卸」を掲げて、全国を7エリアに分けて事業を展開するカンパニー制度をとっていますが、グループ全体で従業員の約3割がエコピープルになっています。多いところでは、首都圏グループで64%、西日本グループでは58%と、半数以上がエコピープルです。今後も積極的に合格者を増やしていきたいですね。

―eco検定導入以前にも環境問題に対する取り組みはありましたか。
eco検定の受験を推進する以前から人事総務部門に環境担当のセクションがありました。当時は「電気を消しましょう」「室温管理を適正にして省エネを心掛けましょう」「ゴミを少なくしましょう」といった初歩的な呼びかけをしていましたが、現在と比べると、環境に対する取り組みは部分的で、まだまだ浅い状態だったと思います。
その後、今私が在籍している経営企画部に環境課を設置しました。そこで環境管理委員会など、新たに“環境”を冠した組織を組成し、従業員の環境基礎知識=ベースの底上げを図ろうと、eco検定を推奨したというのが導入までの経緯です。
環境教育が全社的な取り組みとなり、2018年には全社を挙げて団体受験※をしたこともあります。受験をきっかけに、従業員の環境に対するリテラシーが上がってきたことを実感しています。
※団体受験=3名以上の団体として申込ができる仕組み。申込管理や成績管理がしやすい等のメリットがある。
 環境問題と自社事業を結びつけることで解像度を高めた
環境問題と自社事業を結びつけることで解像度を高めた
―eco検定の受験者・合格者を増やすために、会社として手厚いサポートをされているとも伺いました。
はい。eco検定の合格者は、受験料を全額会社で負担しています。また、受験対策として2015年より「直前ゼミ」を開催しており、もう10年になりますね。
公式問題集の過去問対策をしっかりやれば受かるとは思いますが、せっかく受験するのにそれではもったいない。eco検定で学習する知識を業務に結びつけ、最大限に活用するためにこのゼミで学びを深めてもらっています。
2時間×6回のプログラムで、最初の3回はテキストを分割して解説し、全体を捉える。4回目はテキストの重要なところを深堀りして学び、仕上げの2回では過去問を解くことに加えて、テキストの内容が当社にとってどういう意味を持つのかという視点から解説を行っています。例えば「ここは、当社にとっても大きな課題で、それに対してこういう取り組みをしています」というように、業界の特徴や、当社の具体的な事業と、環境とのつながりを理解できるように説明を加えています。
私自身が受験した時を振り返っても、環境問題の全てを網羅するのはなかなか難しいことだと感じました。しかしその全体像に触れながら、限られた時間の中でポイントを明確にし、自分たちの事業と紐付けて理解することが非常に重要です。

―単純に知識を身に付けるだけでなく、「事業に活かす」という目的を明確に伝えていらっしゃるのですね。
eco検定を通じて学ぶことで、環境の側面から社会が企業にどのようなことを求めているかといった基本的なことを、従業員一人一人が理解できるようになりました。環境問題の理解度が高まることで、アップサイクル商品の開発につながったり、あるいは環境負荷の低い取り組み、例えばペーパーレスの実施や、サプライチェーン全体での環境配慮などの検討・実践につながり、グループ全体への良い影響を感じます。
こうした従業員の環境リテラシーの向上をベースに、当社では2020年に「SDGsステートメント」を策定しました。これに基づいて食品リサイクル施設見学会や処分施設見学会の実施、環境・森林研修などの環境活動を行いながら、「食のマーケティングカンパニー」の進化に努めています。
―具体的な取り組みの実践にもeco検定での学習効果を感じていらっしゃいますか。
当社の事業はプロダクトライフサイクルの様々な場面に関わりがあるので、それぞれの場面において環境に配慮した取り組みができます。たとえば、CO2削減のためにトラック配送の効率化を図る、在庫管理のための温度調整で発生する環境負荷低減のために自然冷媒を使う、廃棄物を極力少なくするためにアップサイクル商品の開発を進めるなど、多面的なアプローチで取り組みを実践しています。

国分グループが結節点となり、様々な主体とパートナーシップを築くことを掲げている。
eco検定をきっかけとして、従業員一人一人が環境問題を「自分ごと」として捉えて理解していることが、これらの取り組みの推進力となっています。受験を通じて環境についての理解を深め、ビジネスパーソンとして一歩踏み込んだ取り組みができるようになることが、eco検定の大きな魅力です。
 対外的な信用、信頼を獲得する
対外的な信用、信頼を獲得する
―お客様との会話などで効果を感じることもあるでしょうか。
そうですね。最近では生活者の方から環境配慮についての問合せや、取引先から「どのような環境活動を行っているか」のような項目を含んだアンケートをいただく機会も増えています。このような場面でeco検定の受験を推進し、従業員への環境教育を行っていることをお伝えできるので、「環境に配慮する取り組みをしっかりとしている」という評価を得られるようになってきました。これもeco検定を通じて、当社の環境リテラシーが上がってきたことの賜物。対外的な信用、信頼を獲得する一助となっています。
また、当社の「サステナビリティレポート」には、グループ各社のeco検定合格者数を明記しています。合格者数といった具体的な数値で示すことで、社外に向けても当社の取り組みを分かりやすくお知らせできますし、従業員のモチベーションアップにもなると思っています。
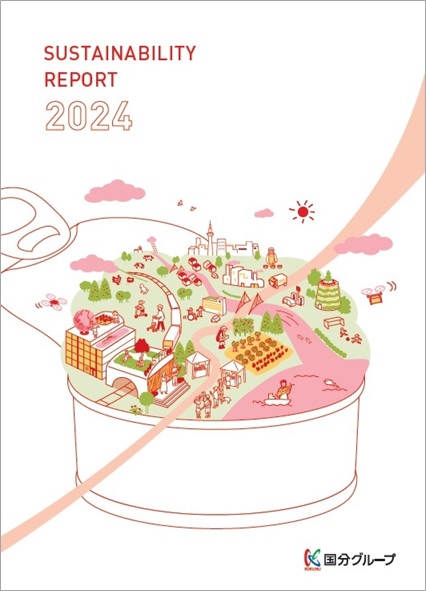
https://www.kokubu.co.jp/sustainability/report/
―最後に、御社のご経験から、今後どのような企業にeco検定を勧めたいですか。
冒頭にお話したとおり、私たち流通業界と環境問題とは、直接的な関わりがあります。食に関わる企業や団体については、広くeco検定の利用を薦めたいですね。
今、当社では「人と社会を調和する商い」といった環境方針を定めています。私たちの事業を、環境に配慮しながら展開し続けることは今後の大きな命題でもあります。そのためには自社だけではなく、サプライチェーン全体で取り組むことが大きな課題です。生産者からメーカー、卸売業、小売業、生活者まで続くサプライチェーンの中で、連携をしながら最適解を探し、接続可能な業界を目指していきたいと考えています。
「環境」というものには、誰もが必ず関わりがあります。食品に関わらず、様々な業界でeco検定を活用して、環境知識を身に付けることは非常に有意義なことだと思います。eco検定に挑戦することにより、さらにもう一歩、環境に対して前向きになる人材が増えることを期待しています。

―「環境に関わりのない人や業界はない」。
すべてのビジネスパーソンが環境知識を身に付けることで、持続可能な社会を実現することこそeco検定の目指すところです。今後も様々な企業でeco検定をご活用し、事業の特徴を活かした取り組みにつなげていただきたいですね。本日はありがとうございました。
 企業概要
企業概要
| 会社名 | 国分グループ本社株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区 |
| 創 業 | 1712年 |
| 資本金 | 35億円(2024年3月現在) |
| 売上高 | 2,068,417百万円(2023年12月期) |
| 従業員数 | 5,051名(2023年12月31日現在) |
| URL | https://www.kokubu.co.jp/ |
※ 掲載内容は2024年12月取材時のものです。
eco検定導入企業3社に、導入の経緯やメリット、今後の展望など
企業におけるeco検定の具体的な活用方法をインタビューした動画を公開中です。是非ご視聴ください!